映画『侍タイムスリッパー』
「斬られ役」に宿る武士の魂に涙腺崩壊。自主制作の粗さを「熱量」がねじ伏せる、今年一番のダークホース。
「出オチ」だと思ってナメてかかると、返り討ちに遭う
タイトルと設定を見た瞬間、「はいはい、よくあるタイムスリップコメディね」と高を括っていました。 江戸時代の侍が現代に来て、カルチャーギャップでドタバタする。 そんな手垢のついたB級映画だろうと、斜に構えて座席に座ったのです。 (正直、ポップコーンを食べ終わる頃には飽きているだろうと思っていました)
しかし、開始数十分でその認識は、半分くらい叩き斬られました。 これは単なるコメディではありません。 実直で、愚直で、どこまでも真剣な「人間賛歌」です。 現代社会に放り出された侍が選んだ道が、ヒーローではなく「斬られ役」だったという設定の妙。 その哀愁と覚悟がスクリーンから滲み出し、気づけば不覚にも涙を流していました。 「ナメててすいませんでした!」と、心の中で土下座しつつ、同時に「もっと金があればな…」という惜しさも感じてしまう作品です。
「働くこと」の尊さが、現代人の心に突き刺さる
この映画がなぜここまで心に響くのか。 それは、主人公の姿勢が、現代の私たちが忘れてしまった「仕事への誇り」を体現しているからです。
彼は、過去を嘆いたり、現代のテクノロジーに文句を言ったりして時間を無駄にしません。 与えられた場所(撮影所)で、与えられた役割(死に役)を、命懸けで全うしようとする。 その姿は、リストラや転職、環境の変化に揉まれる現代のサラリーマンへの、最強の応援歌になっています。 「誰かが主役で、誰かが斬られ役。それでも、その一瞬に命を燃やせるか」 そんな問いかけを突きつけられ、明日からの仕事に対する背筋が伸びるような思いでした。 ただ、そのメッセージ性が強すぎて、後半少し説教臭く感じる部分も無きにしもあらずですが。
「斬られ役」という生き様への深掘り
本作の白眉は、主人公が「斬られ役(きられやく)」という、一見地味な職業に武士道を見出すプロセスにあります。 かつては人を斬るために剣を振るっていた男が、今は「斬られたふり」をして倒れる技術を磨く。 この皮肉で残酷な運命を、映画は決して悲劇として描きません。
「死に様を美しく見せる」 それは、生きることに執着しない武士の美学と、エンターテインメントの極意が奇跡的にリンクした瞬間でした。 彼が稽古を重ね、いかに派手に、いかに無様に、そしていかに美しく死ぬかを研究する姿は、滑稽でありながら崇高です。 そこに「諦め」ではなく「新たな戦場」を見出した男の顔つきが変わっていく様は、鳥肌モノでした。 現代社会において、誰もが主役になれるわけではありません。 しかし、脇役には脇役の、誰にも譲れない「矜持」がある。 そのメッセージが、泥臭い汗と涙とともに描かれるからこそ、私たちの胸を打つのです。 (特に、ショートケーキを初めて食べるシーンの、あの幸せそうな顔。あれだけでご飯3杯いけます)
消えゆく「時代劇」への、狂気じみたラブレター
この作品のもう一つの主役は、「時代劇」そのものです。 撮影所(太秦)を舞台にしているだけあって、作り手たちの時代劇に対する愛と危機感が、画面の端々から溢れ出しています。
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 脚本の完成度 | Sランク(奇跡) |
| 殺陣(タテ) | 本物 |
| 映像の質感 | Cランク(要努力) |
【解説】 昨今、制作数が減り、風前の灯火とも言える時代劇。 劇中のセリフにも「もう時代劇なんて流行らない」という自虐が登場しますが、映画自体がそれに全力で反抗しています。 CG全盛の時代に、生身の人間がぶつかり合う「殺陣」の迫力。 重いカツラをつけ、着物を着て、夏の京都で汗だくになって撮影する現場の熱量。 「古いものを守る」のではなく、「良いものだから残すんだ」という作り手の叫びが聞こえてくるようでした。 ただし、やはり予算の壁は厚く、照明やカメラワークの一部に「テレビドラマ感」や「自主制作感」が拭えない箇所が散見されます。 映画館のスクリーンで観るには、少々画作りが弱く、没入感を削がれる瞬間があったのは否めません。
自主制作(インディーズ)だからこそ到達できた「純度」と「限界」
『カメラを止めるな!』と比較されることが多い本作ですが、共通しているのは「予算のなさ」を「情熱」で凌駕している点です。 もしこれが大手配給の豪華キャスト映画だったら、ここまでの感動はなかったかもしれません。
無名の俳優(失礼!)たちが演じるからこそ、そこに「リアルな生活者」の匂いが漂います。 主人公を演じる山口馬木也さんの、あの実直そうな目。 彼が本当に江戸時代から来たのではないかと錯覚させる説得力は、作り込まれた演技というよりは、役者本人の人柄が滲み出ているように感じました。 また、安田淳一監督が「脚本・監督・撮影・編集」などを一人で何役もこなしているという事実。 これが映画内の「限られたリソースで最善を尽くす」というテーマと完全にシンクロしています。
しかし、同時に「限界」も見えてしまいます。 中盤の展開が少し間延びしていたり、演出が説明過多だったりと、誰かが客観的に「カットしよう」と言えばもっと良くなっただろうな、という惜しい部分も。 情熱は100点ですが、技術的な洗練度は70点。 その凸凹も含めて愛せるかどうかが、評価の分かれ目でしょう。
ラストの「真剣勝負」がもたらす、心地よい窒息感
ネタバレは避けますが、クライマックスの殺陣シーンについて触れないわけにはいきません。 ここでは、単なる演技を超えた、ある種の「ドキュメンタリー」が展開されます。
「カット」の声がかかるまでの、永遠にも思える静寂と緊張。 竹光(たけみつ)ではなく、真剣のような重みを感じさせる太刀筋。 互いの呼吸、筋肉の収縮、瞬き一つ許されない極限状態。 見ているこちらまで呼吸を忘れ、酸欠になりかけました。 それは、フィクション(映画)とリアル(侍)の境界線が溶解する瞬間であり、映画というメディアが到達できる一つの到達点だと思います。 ただ、ここに至るまでの「現代への順応プロセス」がコミカルだった分、ラストのシリアスさとのトーンの落差に少し戸惑う観客もいるかもしれません。 私はそのギャップこそが魅力だと感じましたが、人によっては「急に重い」と感じる可能性もあります。
結論:今年、最も「応援」したくなる映画
大作映画のような派手な爆発も、有名なアイドルも出ていません。 映像の粗さもあるし、ツッコミどころも探せばあります。 しかし、ここには「映画」にとって最も大切な「心」があります。
笑って、泣いて、熱くなって。 映画館を出る時には、少しだけ世界が優しく見え、明日からの仕事も「まあ、やってやるか」と思えるようになる。 そんな魔法のような効能を持った作品です。 78点。 「傑作!」と手放しで褒めちぎるには、映像的な弱さが気になりますが、観たことを後悔する確率は限りなくゼロに近いでしょう。 時代劇ファンはもちろん、日々の生活に疲れている全ての人に処方したい、特効薬のような映画です。 (完璧な映画を求める人には向きませんが、熱い映画を求める人にはマストです)
作品情報
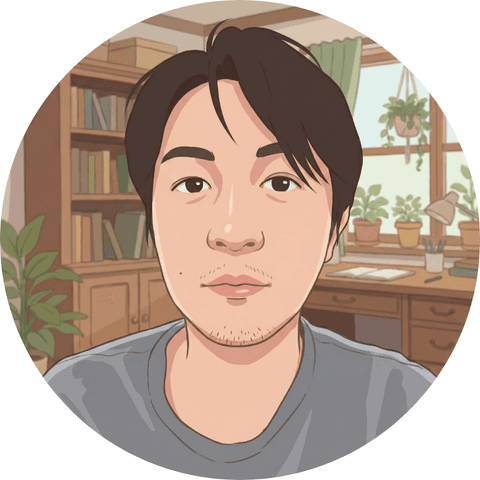
小林 祐太
TV60編集長。脚本構造と映像技術の分析に基づいた『構造批評』を得意とする。ガジェットレビューでは、スペック数値よりも『生活への定着度』を重視し、最低1ヶ月以上の実使用を経た上での評価を徹底している。
CINEMAの他の記事

映画『国宝』
「芸」という名の地獄めぐり。スクリーンから漂う血と汗の匂いに、開始10分で窒息しそうになりました。

Disney+『SHOGUN 将軍』
「どうせハリウッドの勘違い日本でしょ?」という偏見は、開始5分で切腹させられます。真田広之の執念が生んだ、歴史的傑作。ただし、疲れます。

映画『MONDAYS/このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』ネタバレなし感想・評価|全社畜が泣いて笑う、共感度100%のお仕事ムービー【レビュー】
「部長、同じ一週間を繰り返してます!」気づかない上司、終わらない仕事、迫る納期。絶望的な月曜日を繰り返す若手社員たちの奮闘を描く、極上のお仕事タイムループコメディ。
この記事をシェアする